Lancelot Biggs Cooks a Pirate by Nelson S. Bond
- 初出:ファンタスティック・アドヴェンチャーズ 1940年02月号
- →電子化:Internet Archives
- →和訳(公開者による):この文書 2019年07月26日~08月11日

「言っておくが」と海賊は冷たい口調で言った。「一服盛ろうとか、つまらん了見を起こすんじゃねえぞ」
画:ジュリアン・クルーパ (Julian Krupa)
『ビッグス、海賊を料理する 宇宙船乗りランスロット・ビッグス第二話』ネルスン・ボンド著
1
騒動の元凶はスロップスだった。ご存じのとおり、スロップスは悪いコックではない。端的に言うならば、そもそも彼はコックの名に値しないのである。彼の“タピオカ澱粉料理”のヘビーローテーションには誰もが愛想をつかした。朝食はタピオカ、昼食もタピオカ、夕食もタピオカ。連日である。茹でタピオカ、煮込みタピオカ、そして極めつけは“タピオカのフリカッセ”。
ああ! 考えてみてほしい。宇宙貨物船で月二回も地球=金星間を飛ぶわたしたちにとって、このタピオカ攻めがどれだけ苦痛だったか。タピ……いや、この言葉を口にすることすらも我慢がならない。
宇宙の古強者、ハンソン船長の鉄の胃袋ですら遂には陥落した。次にサン・シティ宇宙港に着陸したとき、船長は厳然と言い渡した。
「スロップス、お前はクビじゃ。そうじゃ。船を降りてもらう」
こうしてシェフ(自称)はサタン号から追放された。スロップスは着替えと清算金とハーモニカと、そしてタで始まるあの物質のストックを持ってどこかへ去って行った。
サタン号はコックを欠いたままサン・シティの乾ドックで立ち往生することになった。船長はベテランとしての顔をフルに使って代わりの料理番を探したのだが、地球への輸出品――ペプシンを始めとした医薬品、そしてメケル芋やクラブ豆も一・二コンテナあった――を積み込み終わったときも、全く人材は見つかっていなかった。
離陸予定日時の一時間前、船長は通信室にふらりとやって来た。船長はわたしの肘掛け椅子にどっかりと腰を下ろすと、ごま塩頭を神経質に掻いた。
「まずいぞスパークス」と彼は弱音を吐いた。「スロップスのクビを切ったときは良いことをしているつもりじゃった。しかし……」
「船長のご英断に異を唱える者はいません。あなたはサタン号の乗務員十四人の命を救ったんです。もう一皿でもあのスライム料理を口にしていたら、反乱か殺人が起きていたでしょう」
「しかし」と船長は心配そうに言った。「後一時間で地球に出発せねばならん。なのにコックはいない。一体どうしたもんじゃろうか?」
そのとき一等航空士のランスロット・ビッグスが入って来た。彼は提案した。
「スロップスを呼び戻しましょうか? やつならパレス・バーでぐだを巻いているのを見ましたが」
「ノー!」と、わたしと船長は同時に叫んだ。
ビッグスはちょっと傷ついたようだった。人並外れて突き出した喉仏がひくひくと上下した。ビッグスは自己弁護的に言った。「ともかくですね、タピオカ澱粉が身体に良いことは事実です。その栄養素のうちわけは――」
「黙らんか!」と船長が噛みついた。
今日の船長は人の意見に耳を貸すような雰囲気ではなかった。特に、ランスロット・ビッグスの意見などには。おそらくは、先日の“錬金術ビジネス”が原因だった。鉛製のフォレンジ箱を宇宙線に晒してプラチナに換えようという、夢いっぱいの遊弋飛行は、完全な失敗に終わった。会社は船長を厳しく叱責した。なので船長はこのアイディアの出どころであるビッグスに恨みを抱いたのだ。
「これ以上“あの物質”のことを口に出す馬鹿者がいたら、わしは殺人すら辞さんぞ!」
ビッグス航空士は心外そうに言った。「ぼくはただ良かれと思って提案しただけですよ」
「良かれと思って?」と船長は辛辣な口調で言った。「余計なお世話じゃ。お前の提案なぞ何の役にも立たん。これ以上わしの前をうろうろせんでくれ。分からんか? とっとと出て行くんじゃ」
ひょろ長の一等航空士は踵を返して部屋から出て行きかけた。そのとき、突然船長の頭に天啓が舞い降りたらしい。
「いや、待った! どこへ行くんじゃね? ビッグス航空士」
ビッグスはどもりながら答えた。「だ、だって……。いま船長が出て行けと……」
「いやいや済まんかった。お主の善意を無駄にするつもりは無かったんじゃ。のうミスター・ビッグス。お主のようなインテリのおつむの中には、さぞかし色んな知識が詰まっておるんじゃろうな? よもや料理という芸術に関して何か知っておるということはないかの?」
「料理ですか?」とビッグス。「ぼくがですか? いいえ船長。何も知りません。ですがそれほど難しいこととは思えませんね。つまるところ、料理とは化学の応用技術の一つに過ぎません。言ってみれば各種の有機化合物を一酸化二水素に溶かして、適度な高温下で――」
ハンソン船長は毒気を抜かれてポカンとした。船長はわたしにささやいた。「スパークス。やつは何を言っておるんじゃ?」
「ビッグス航空士が言っている意味は」とわたしは通訳した。「料理とは、水と食材を合わせて熱するだけの簡単な仕事だということです」
「おお! そういうことじゃったか」船長はにんまりと笑った。「それならば問題は解決じゃな。ミスター・ビッグス、お主に新しい役職と制服を与えよう。新しい持ち場はデッキの下の、三番目のドアを開けたところじゃ」
今度はビッグスがポカンとする番だった。突き出した喉頭がぐるぐるとインメルマン・ターンのごとき動きを見せた。
「はあ? でも船長、ぼくはコックじゃありません。一等航空士ですよ!」
「それはさっきまでの話じゃ」と船長が冷然と答えた。「現時点ではコックじゃ。
2
ビッグスの説は正しかった。確かにそのとおりだった。だが、ランスロット・ビッグスがそのことで難敵との対決を余儀なくされる運命にあることを、この時だれも予想だにしていなかった。
最初の食事時間がやってきた。地球時間での昼過ぎ、わたしたちサタン号の乗務員一同は恐る恐る食堂へ集まった。わたしも昨日今日宇宙に出てきた小僧っ子ではない。ましてやサタン号のようなおんぼろ貨物船に通信士として乗っていれば、けっこうイレギュラーな経験もするものだ。しかしビッグスの料理がいったいどのようなものかは想像も付かなかった。わたしは最悪の事態も覚悟していた。
料理番ビッグスの手腕はまるで手品だった。彼はシルクハットから素晴らしい御馳走を取り出した。フライド・チキンのグレイヴィ・クリーム掛け。ホット・ビスケット。ヤム芋の砂糖煮。クラブ豆のシチュー。無国籍風レーズン・パイ。わたしたちは舌鼓を打った。そして仕上げはサタン号の長い歴史上で最初にして最高の、本当に美味しく淹れられたコーヒーだった。
他の乗務員が何を考えていたか、わたしには分からない。なぜならば誰も一言も口を利かなかったからだ。誰もが自分の口に料理を送り込むことに没頭していた。一切のコミュニケーションはその場から消え去った。わたしたちが言葉を発さずにひたすら食いまくる様子と来たら、火星ニシンさながらだった。チキンの最後の一切れを食べ終わり、ベルトをゆるめ、わたしはようやく席を立ってよたよたと厨房に向かい、ビッグスと顔を合わせた。
「ビッグス!」とわたしは問い詰めた。「あんた、料理の名人だってこと、どうして隠していたんです?」
ひょろ長の若者は羊のようにもじもじとし、そして答えた。「ぼくの料理はそんなに美味しかったかい? スパークス」
「美味しいなんて生易しいもんじゃない! まさに絶品でしたよ。生まれてこの方、こんな料理を食わせてもらったのは初めてです」
ビッグスはほっとした顔をした。「そう言ってもらえると嬉しいよ。実はね、料理らしい料理を作ったのは今日が初めてだったからね」
「初めてですって!? まさか、本当ですか?」
「んんん、まあね。けど料理の本なら厨房にたくさんあったからね。それに料理がどういう原理なのかは昔から想像していたとおりだったから、実践に移しただけのことさ」
ビッグスはわたしに慎ましい笑顔を見せた。わたしはふと思った――このひょろ長の変人が天才であることを、他の連中は気づいているのだろうか? そしてそう思ったのはこれが最後にはならなかった。
「実を言うと、料理ってなかなか面白いと気づいたよ、スパークス。船長にも言ったとおりだけど、これは初歩的な化学の問題なんだ。鍋やフライパンは試験管と同じだし、コンロはブンゼン灯みたいなものさ」
わたしは恐れ入ってしまった。「ぐうの音も出ないですよ、ミスター・ビッグス。あんたは自分の理論のとおりに事が運ぶと信じていたんですか?」
「もちろんだよ。“理論が第一”。それが、何をやるにしてもぼくのモットーなのさ。ぼくはそれでずっと成功を修めてきたんだ」
ビッグスはちょっと得意そうだった。彼は続けて言った。「そういうわけで、この飛行の間、料理のことはぼくに任せてくれ。実験材料の食材は豊富にあるからね。次の食事については――」
そのときインターカムでわたしの番号が呼び出された。わたしはすぐに受話器を取って怒鳴った。「スパークスです! どうかしたのか?」
呼び出し元は無線室。相手はわたしの留守番役だった。「スパークスかい? 上がって来てくれないか。サン・シティから通信だ。悪いニュースがある」
「了解。今行く!」と叫んでわたしは通話を切った。ビッグスに「じゃ、また後で」と言いおいて、わたしは無線室への縄梯子を急いで登った。留守番役の男が待っていた。ハンソン船長と、副官のトッド航空士もそこにいた。三人とも表情が険しかった。絶望と恐怖の色があった。わたしの留守番役がもろい通信ワイヤを無言で手渡してきた。サン・シティ宇宙港からの暗号通信だった。このわたしにとっては暗号文も、英語も
『金星から地球に航行中のIPSサターン号のハンソン船長へ。直ちに引き返して護衛艦と合流されたい。海賊ヘイクが貴船の軌道上、三・一五プラス九〇九ポイントで発見された。署名:
ハンソン船長とわたしは見つめ合った。わたしは自分の顔から血の気が引くのを感じた。そして腹部には異様な鈍痛が襲ってきた。
「ヘイク! あの“卑劣漢”ヘイクか!」とわたしは叫び声を上げた。
「そうじゃ。しかし最悪のポイントはそこではない。スパークスに教えてやってくれ、ミスター・トッド」
トッドは乾いた唇を舐めてから、重い口を開いた。「わ、われわれは実にまずい状態にある。本船は二十時間前に最大限まで加速し、エンジンを止めて自由落下中だ。そして自由落下は通常だと約九日間続く。その期間を利用して、ギャリティ機関長はすでに第三
ピンと来ないわたしは質問した。「分解したなら、急いで組み立て直せばいいんじゃないんですか?」
「無理だ。ギャリティは筐体が劣化していることを発見したため、鋳造し直そうと、いったん溶解してしまった。原状復帰にはどうやっても丸二日はかかる!」
3
地球から出たことのない素人さんに分かりやすく言うと、サタン号は俎板の鯉だった。ハイパトミックとは、宇宙船を推進するためのエンジンである。今回の場合だとそのうちの一つが不調だったのだ。宇宙船は宇宙空間では噴射を止めていわゆる“惰行運転”をするのが基本だから、機関科の連中がその間に本格的な整備をするのは普通のことなのである。トッド航空士が言うように、このような作業が完了してハイパトミックが使用可能になるには最低でも二日か、あるいはもっと時間がかかる。
しかし、よりにもよって相手が悪名高いヘイクなのだ。通称“卑劣漢”ヘイク。惑星間空間には海賊が珍しくないが、中には(犯罪者にしては)良い人間もいるのだ。例えば“雲雀”のオーデイと呼ばれている男は、何を略奪したかの明細書を几帳面に作成し、署名した上で被害船の船長へ紳士的に交付するのだ。ある時などはとある不定期貨物船の船長に積荷を取られたら首を括らなければならないと泣きつかれて、何も取らずに見逃したという逸話もあるくらいだ。ある時には豪華客船を襲ったが、その目的は金品を奪うことではなく、新しいミス・ユニバースからキスを奪うことだった。
だが大半の宇宙海賊はスカンク以下の連中だ。読者諸君が想像しうる限り最低の悪漢ぞろいと言っても良い。そして、それに十を掛けて無限を足したものが、“卑劣漢”ヘイクなのだ。
ヘイクは殺人狂だった。人類が戦争や暴力に明け暮れていた暗黒時代への先祖返りだ。この男の目的は金品ではなく、むしろ暴力と殺人だった。ヘイクは常にサディスティックな欲求を発散する場を求めていた。そして、主たる発散方法はサタン号のような貨物船を襲って、積荷を奪い、そして船隔に小さな空気漏出孔を開けることだった。もちろん、哀れな被害船から救命ボートや宇宙服を奪った上でのことである。
わたしは、小惑星サーゴサでのことだったが、一度だけヘイクの被害に遭った船を見たことがある。船員たちはみな喉を切られて死んでいた。遺体は人間の形には見えなかった。凍結した血塊がそこらじゅうに浮かんでいた。
“卑劣漢”ヘイクとはそういう男だった。そしてわたしたちは身を守る術も無く、ヘイクの待ち構えている軌道を飛んでいくしかなかった。
ハンソン船長が固い表情で言った。「言うまでもないが、やつらを避ける手段はない。かくなる上は、六分の一口径の
「駄目ですよ、船長。そんな真似をしたら
“アンピー”とは、金星原産のエネルギーを食べる動物である。電気に対する飽くなき食欲は、宇宙船が惑星のヘヴィサイド層を通過する際に絶好の緩衝材として活用されている。こいつを利用するというのは悪い考えではない。だが船長は首を横に振った。
「いや、役には立たんじゃろう。アンピーは電撃は吸収してくれるが、熱線は吸収してはくれん。やるべきことはたった一つ。宇宙パトロールの護衛艦に至急で打電するんじゃ。そして、ヘイクに捕まる前に救助してもらえることを祈るのみじゃ」
通信士の出番だった。わたしは留守番役を押しのけて、震える手で通信した。“SOS”(助けて)がエーテル空間に満ちた。そして“PDQ”(大至急)も追加で。
サン・シティからはすぐに応答があった。護衛艦を全速で向かわせるので、心配するなと……
だがわたしの膝の震えを止める役には立たなかった。
4
ランスロット・ビッグスには、絶対確実に頼れることが一つあった。それは、彼が間違った時と場所に鼻を突っ込んでくることである。わたしたち三人が深刻な空気で押し黙っていると、ドアが勢い良く開き、料理番兼一等航空士兼雑用係がひょこひょこと入ってきた! その顔はわたしたちとは対照的に、歓喜の色に満ちあふれていた。ビッグスはにたにたした表情を放射性物質のように四方八方に振りまいていた。やつは楽しくて仕方がないと言った様子で口を開いた。「ねえ、船長――」
「出て行け!」と船長が言い捨てた。「考え事の邪魔じゃ」
「まあそう言わずに見てくださいよ」と言いつつビッグスはハムのような手を開いた。手のひらには小っちゃな灰色のネズミが乗っていた。ビッグスはネズミを床に置いた。「ぼくの発見した四号試薬の効果をご覧ください。この薬のユニークな働きにより――」
「出て行くんじゃ!」と船長は語気を強めた。「今、お前と遊んでいる暇はない」
「でも本当に面白くて――」
確かにネズミの行動は奇妙だった。一般的に、ネズミは臆病な生き物である。にも関わらずこのチビ公は床に下ろされ、巨大な人間たちに囲まれても、部屋の隅の暗がりに逃げ込もうとする素振りを見せなかった。ネズミはトッドにゆっくりと近寄ると、その靴に人懐っこく鼻をこすりつけた! まるで昔からの馴染みであるかのように。ミスター・ビッグスはくすくすと笑った。
「どうです? 船長、ネズミの行動の秘密を知りたくありませんか? ご説明いたしましょう。これはひとえにプロラ……」
「ミスター・ビッグス!」と叫んだ老船長の顔は憤怒で真っ赤になっていた。「今はそんなナンセンスに関わっている状況ではないんじゃ。一時間以内、下手をすると一分以内にもわしらの命は無くなるかもしらんのじゃ! 分かったか? とっとと出て行くんじゃ!」
ビッグズはしゃちほこばって答えた。「イ、イエッサー!」
彼はトッドの靴紐とたわむれている小動物を回収し、ポケットに収めると、回れ右して部屋から出て行った。出て行きながら、ビッグスはわたしに向かって意味深な手振りを投げかけた。わたしはうなずいた。士官たちは大問題で手いっぱいで、わたしに注意を払っていなかったので、わたしはひょろなが男に続いて部屋を出た。
「何か起きたのかい? スパークス」とビッグス。
わたしは包み隠さず説明してやった。ビッグスにも知る権利はある。本当は、サタン号の誰もが、自分がこの世とおさらばする理由と日時を知る権利があるのだ。
「だけど他のやつには他言無用ですよ」とわたしは注意した。「告知は、
ビッグスは目を真ん丸に見開いた。「“卑劣漢”ヘイクか! 何てこった。船長の立場はお察しするよ」
彼は少しの間沈思黙考した。そして突然叫んだ。「そうだ!」
「何ですか?」
「聞くところによると、ヘイクは船を拿捕したら、穴を開けて殺す前に大宴会をやらせるそうだね?」
「そうらしいですけど」とわたし。「まさか一服盛ろうとでも考えているんですか? 馬鹿なことを言わないでくださいよ。当然、毒見をさせられるのはあんた自身ですよ」
「心配ご無用。ぼくのアイディアはちょっと違うんだ――だけど今はまだ言わない方がいいかな。ところで、生理化学の本を持ってないかい?」
「自分の本棚にあります」
「よし! 持ってきてくれるかい? 事情は後で説明するよ」
わたしの本をポケットに突っ込むと、ビッグスは竹馬に乗ったコウノトリのようにひょこひょこと小走りで厨房の方へと消えて行った。だがその時のわたしには、彼の奇矯な外観や内面を笑っている余裕はなかった。
不吉な金属音が聞こえて来たからだ。わたしの目は異音の発生源に引き付けられた。誰かが、船外から、宇宙服の手袋をはめた拳で
わたしは通信室に駆け戻った。「船長!」とわたしは叫んだ。「エアロックに誰かいます! たぶん――」
ヘイク一味に違いなかった。
5
読者諸君は意外に思うだろうが、ヘイクの風貌は人殺しのようには見えなかった。ヘイクは貫通銃を構え、すたすたと船内に入ってきた。武装した六・七人の悪漢どもがいつでも発砲できる態勢でボスに続いた。さらに数人の一隊が廊下を駆けて行った。機関室と操縦室を制圧するつもりだろう。
ヘイクは
その声も穏やかだった。「抵抗しないように部下に命令してもらおうかな? 船長どの。その方が賢いぞ」
ハンソン船長は答えた。「ヘイクよ。本船はお主に降伏する。じゃからわしの部下に手出しはしないでくれ。条件はそれだけじゃ。無駄に逆らうつもりは――」
「まあそう焦りなさるな、船長」とスマートな海賊が眉を上げながら言った。「命乞いはまだ早い。ご存じかと思うが、わが海賊団には所定の手順がある。“お楽しみ”の前に、やるべきことは沢山あるのだよ」
その言葉を聞いていて、わたしはこの男のがどうして“卑劣漢”の二つ名を持っているのか腑に落ちた。この男の問題は、黄金の髪でも、薔薇の頬でも、柔らかな唇でもない。問題は、内面が腐っていることなのだ。眼にそれが現れていた。眼球はきょろきょろと落ち着きなく、ぎらつく光を帯び、眼差しは明らかに人を見下していた。瞳の奥に燃える炎は、来たるべき“お楽しみ”への期待を隠し切れていないようだった。
ヘイクは悪魔だった。超小型版とは言え、悪魔には違いなかった。これまでに聞いていた噂は全て本当だった。この男から、一切の慈悲は期待できそうになかった。ヘイクは猫がネズミをもてあそぶのように、面白半分にわたしたちの命を奪うだろう。やつがサタン号を後にする時、わたしたちは小惑星サーゴサで見た被害者のように生命のない物体に成り果てているだろう。
ヘイクは再び口を開いた。柔らかで、音楽的な声音は、宇宙空間で貨物船を拿捕した海賊というよりも、地上の宇宙港で所定の検査に来た税関職員のようだった。
「積荷は当然いただく。すでにわたしの部下が積み替えている最中だ。そして、諸君らとお別れする前に若干やりたいことがある。わたしたちは、手狭で簡素な船で何カ月も宇宙を航行している。食事も贅沢品は全くない。そこでだ。この船の備蓄はどうなっているかね? 上等な食材は? ワインは? 最後の晩餐を開くのに充分なだけ揃っているかね?」
ハンソン船長は腹をくくって答えた。
「たっぷりあるぞい。わしの部下に危害を加えないと約束するなら、いくらでも提供しよう」そして、少し躊躇してから言った。「人質が要るならわしを連れて行ってくれ。わしは一向に構わん。だから――」
「いや、いや、駄目だよ船長! そういうことは出来かねる。最期の時をかわいい部下と一緒に過ごしたまえ」ヘイクの目がきらりと光った。「わたしの評判は知っているだろう? まあ、わたしに言わせれば過小評価なのだがね。このヘイクの顔を見て生き延びた者はこれまでに一人もいない。面が割れるわけには行かないからね。わたしは自分の顔を見た人間は必ず始末することにしている。職業上、当然のことだろう?」
ヘイクは振り向いて部下たちに命令した。「身体検査だ。武器を持ってたら取り上げろ」そして、わたしたちに無造作に言った。「積荷を移し終わったら、食事にしてもらおう。サタン号の食堂で大宴会を行う」
6
一般人からすると事の成り行きが――なぜ乗り込んできたヘイクにわたしたちが全く抵抗しなかったのか――理解し難いかもしれない。だが恥じる必要はない。わたしも『火星マガジン』や『週刊宇宙航路』なら読んだことがある。その種の三文雑誌の寄稿者たちは、宇宙貨物船の船長と言えばジョン・ポール・ジョーンズ(訳注:アメリカの軍人。独立戦争の英雄。)のような鉄腕の豪傑ぞろいだと信じているようだ。だが、当然そんなことはない。サタン号は、ヘイクの快速船に比べればのろまな牛のようなものだ。ハンソン船長は正気の人間が取り得る手段を取っただけだ。あの状況下ではただただ悪党どもの機嫌を損ねずに時間を稼いで、護衛艦の到着を待つより他にない。
こうして我々サタン号一同は二時間以上もの間、ヘイクの一味に取り囲まれて耐えることになった。海賊どもは、積荷の中でかさばらない割に価格の高いものを根こそぎ奪い去った。こちらの乗務員の一部――主に機関室の連中――が荷物運びを手伝わされた。小惑星帯のどこかの隠れ家から襲来した無法者どもは、容赦がなかった。
“卑劣漢”ヘイクは、トッド、船長、そしてわたしを引き連れて厨房に向かった。やつの目は油断がなかった。厨房に降りて行ったわたしたちは、ランスロット・ビッグスが座って静かに本を読んでいる光景を見出した。
ヘイクは落ち着いて、猫なで声で言った。「きみがこの船のコックかね?」
ビッグスが答えた。「ウーム……フーム……」
「こっちを見たまえ」と犯罪者が言った。「よろしい、料理番くん。食事の準備を頼む。豪勢な食事だ。血の滴る肉に、新鮮な野菜をケチケチせずに使ってくれ。実を言うと――」とヘイクは船長にゆっくりと話しかけた。「わたしたちは、缶詰食品には心底うんざりしているのでね」
ハンソン船長はうなり声で答えた。だがビッグスは落ち着きなく言った。「そ……それなら貯蔵庫から材料を取ってこないと。この厨房は見てのとおり狭いので――」
ビッグスは海賊に気圧されているようだった。
ヘイクはうなずいた。「結構。だが一つ言っておこう。毒を盛ろうとか、古臭い真似はやめておくことだ。以前、スピカ号のシェフがそういう細工をした。馬鹿なやつよ。その男が上げた汽笛のような悲鳴を、わたしは永遠に忘れることはないだろう」
確かにそうだろう。下劣なやつめ! わたしは切望した――ビッグスが変な真似をせずに居てくれることを。ひょろなが男はそれ以上ヘイクに引き留められることなく、厨房から出て行こうとした。
ビッグスはようやく正気に戻ったようだった。彼は震え声で言った。「最高の仕事をさせてもらいますよ。ただし、当然ある程度の時間はいただきますが」
「良いだろう」とヘイク。「しっかり頼むよ。さて、紳士諸君――?」
海賊の親玉はわたしたちを連れ、厨房を離れた。わたしが最後尾だった。ドアを閉めようとした時、ビッグスがわたしのポケットに何かを突っ込んだ。彼はささやいた。「スパークス……味方全員に……呑ませてくれ……こっそりと……」
7
一瞬、希望の炎がわたしの心中で燃え上がった。ビッグスが袖に何を隠しているのかは見当も付かないが、この男なら――この男の発明工夫の才なら――血に飢えた海賊どもを何とかしてくれるのではないかと、わたしは夢見た。しかし、隙を見てポケットの中を確認したとき、二・三分前に抱いた希望はもろくも崩れた。
ビッグスが渡して来たものはただのペプシンだった。何の変哲もない、普通のペプシン。金星で積み込んだペプシンだ。
ビッグスは恐怖のあまり気が狂ったのか? わたしはこの役立たずの薬品を投げ捨てようかと思ったが、思いとどまった。結局のところ、ビッグスにはビッグスなりの考えがあるのかもしれない。どんなに可能性が小さい賭けだろうと、この状況ならやってみる価値はあるのではないか……?
そうして、わたしはこの薬品を徐々に船内に浸透させることにした。まずはスチュワードのダグ・エンダービーに半分ほど渡してボイラー夫の連中に呑ませるように言いつけた。階下に向かい、ギャリティ機関長に会った。部下たちに呑ませるようにペプシンを人数分渡した。トッドにも一錠押し付けた。不審な目をしていたが、わたしが目で促すと嫌々ながら呑み込んだ。わたし自身? もちろん呑んだ。特段不味くはなかった。死ぬ直前にわざわざ嫌な味を感じる羽目にはならなかった。
わたしが薬を呑ませるに至らなかった唯一の人間は、ハンソン船長である。“卑劣漢”ヘイクが船長から目を離さなかったからだ。実際問題、やつはわたしたち全員を鵜の目鷹の目で見張っていた。この殺人狂の小男は実に抜け目がなかった。夕食が運ばれてくる直前、ヘイクはわたしの心臓を危うく止めるところだった。「何を噛んでいるんだね? スパークスくん。ガムかね?」
その言葉は脅威でもあったが、逃げ道も含んでいた。わたしは内心びくびくしつつも、うなずいた。「そうです。お一ついかがです?」
やつはお上品に身震いした。「いや結構。ガムを噛むというのは、実に野蛮な風習だよ」
間一髪! わたしはこの場を何とか凌いだのだった。
8
ビッグスが船内放送で晩餐の報せを鳴り響かせると、人々は混み合った食堂に集まった。誰でも腹は減る。堅気で働き者の宇宙船員と無法の極みの宇宙海賊が、同人数、同じテーブルに着いて同じものを食べることになった。
狂気の沙汰? そのとおりだが、全てはヘイクのせいだ。ビッグスに言わせれば、やつは目立ちたがり屋だ。しかしながらヘイクは危険は冒さなかった。わたしたちは武装解除されていた一方、ヘイクの一味は歩く武器庫だった。こうして狂気の大宴会が始まった。表面上、全員が仲良く席に着いていた――そのうちの半数、サタン号の乗務員は屠殺場に送られる前に太らされている家畜も同然だったのだが。
「死刑囚の大飯ぐらい」という古いことわざがあるが、その時のわたしたちはまさにそれだった。そして海賊たちの食いっぷりもわたしたちに負けずだった。なぜならば、料理は応用化学だと断言する新料理人ビッグスは、二番目の作品においても自説の正しさを証明して見せたからである。
読者諸君の食欲を刺激するために、その料理の一端を紹介しよう。まずはシェリー酒入りの冷製コンソメスープ。続いてモーゼル・エルデナー・トレップヒェン風の鱈料理。これには
だがここまでは前奏曲に過ぎなかった。メインは羊の
そしてパイパー・エドシックの65年もののシャンパンが出された。続いて食後のコーヒー。そしてリキュール……
とうとう“卑劣漢”ヘイクが言葉を発した。「この酒は持って帰ることにしよう。この場で酔い潰れるわけにはいかないからな。酒を……いや……うん、これで充分だ。なあハンソン船長?」
船長はうなずきつつ、操縦室の方へ意味深な目配せをした。わたしたちは席を立った。トッドも続いた。驚いたことにビッグスも仲間に加わった。船長に話しかけるヘイクのしみじみとした口調を、わたしは一生忘れることはないだろう。「われわれは宴会を大いに楽しませてもらったよ、船長。だがご理解いただいているとおり、次のステップに進まねばならん。われわれの……あー……義務だからな」
船長は冷静に言った。「ヘイクよ。サタン号を沈める前に、救命ボートをくれんかの?」
ヘイクは白々しく答えた。「船長。それこそ、わたしがまさに考えていたことだ。しかし不幸なアクシデントがあってね。わたしの部下が不注意にも救命ボートに一隻残らず穴を開けてしまったのだ。お望みなら壊れたボートに命運を託すのは自由だが――?」
ヘイクめ。けだもののような奴だ! トッドを見ると、わたしと同じことを考えていることが目から読み取れた。ヘイクさえ捕らえてしまえば、チャンスはある。わたしは気を引き締めた。もし首領を人質にすれば、海賊たちは人質を傷付けるのを恐れて身動きが取れなくなるだろう。わたしとトッドが二人で同時に掛かれば、ヘイクが銃を抜くよりも早く――
その時ランスロット・ビッグスが邪魔をした。わたしに向かって大きな声で叫んだ。「ダメだ! やめろスパークス!」
そしてヘイクに対し、静かに話しかけた。ほとんど優しげな口調だった。「あのですね、ヘイクさん。全部誤解なんです。この二人はあなたに殺されるのを恐れているんですよ。でもそんなことはあり得ませんよね? あなたはそんな悪い人じゃないですよね?」
9
ヘイクの唇が引きつった。海賊の首領は子供のように涙を流し、顔をくしゃくしゃにして抗議した。
「殺すだって? わたしが? 彼らを? まさか、そんなことをするはずがないよ! わたしはサタン号の諸君が大好きだ。親友じゃないか!」
ヘイクは貫通銃を抜いて、床に投げ捨てた。そしてビッグスと肩を組んだ!
トッド航空士がかすれ声でつぶやいた。「神様仏様、こりゃ一体どういうことだ?」
わたし自身は茫然と突っ立っていた。だが気を取り直すと、わけの分からないシーンが繰り広げられている前で、屈んでヘイクの銃を拾った。
「やつめ、頭のヒューズが飛んだようだ」とわたしは早口で叫んだ。「取り押さえるんだ、トッド! ビッグスさん、あんたと俺は残りの海賊どもを――」
だがビッグスは泰然自若として言った。「落ち着いてスパークス。焦る必要はないよ。見てくれ」
ひょろ長の料理番は壁に歩み寄り、
彼らは互いに抱擁し合い、肩を組み、友愛の言葉を掛け合っていた。全くもって珍妙な光景だった。わたしは当惑した。髭面で片目の無法者が膝の上で仲間をあやしていた。別の屈強な大男は、涙を流すには倍以上大き過ぎたが、相方に負ぶわれて泣いていた。
わたしは理解が追い付かずヴィジプレートを凝視し、再度凝視した。「これは……一体……?」
ビッグスが突然言った。「スパークス! きみは船長にペプシンを呑ませなかったな?」
「機会が無かったんだ。でも、なんで……」
ヴィジプレートの中では船長が“卑劣漢”ヘイクに懐かれていた。二人は同じ椅子に座り、優しい言葉を掛け合い、互いの髪を愛情深く撫で合っていた。わたしが見た時、ちょうど親父が屈み込み、海賊の額に熱いキスをしたところだった!
その直後、歓迎すべき横やりが外部から入った。緊迫した声が無線機から呼びかけて来たのである。「サタン号、応答せよ! サタン号、応答せよ! こちらは太陽系航空パトロール、巡洋艦アイリス号だ。大丈夫か? 本艦は二十分以内に接舷できる予定だ――」
10
その後、“卑劣漢”ヘイクとその一味は友愛の情に酔い痴れたまま、ほとんど抵抗らしい抵抗もできずにパトロール艦に逮捕され、金星の監獄へ送られた。
わたしたちは無線室で集まっていた。そこにいたのはトッド航空士と、ギャリティ機関長、そしてランスロット・ビッグスとわたしだった。ぼんやりした目付きで、まだ混乱している船長もいた。ハンソン船長は、彼のいわゆる“仲良しタイム”の間、実につらい体験をしたのだった。
わたしには今回の手品の種明かしはできない。だからビッグスに率直に尋ねた。「どういう仕掛けだったんですか? ビッグスさん。あんたが料理に何かを盛ったってことは分かってます。そしてあらかじめペプチンを呑んでおけば、それを打ち消す効果があったことも分かってます。問題は、それが何かってことです。人間をあんな風にしてしまう薬が存在するなんて、聞いたことがありませんよ?」
ビッグスはにたにたした。のどぼとけがゆっくりと動いた。「薬とは少し違う。プロラクチンという化学物質だよ。覚えていないかもしれないけど、今回地球に運んでいた積荷の一部だよ」
「プロラクチンだって?」とトッド。「どういうものなんだい?」
「下垂体の抽出物です。人間の愛情を司るホルモンです。動物に子育てをさせているのもこれです。プロラクチンを投与すれば、オンドリに卵を抱かせるのも、オス猫に授乳をさせたり、乳の出が悪いメス猫を正常にしたりできるんですよ。だからプロラクチンは俗に“母性愛の素”と呼ばれています」
「なるほど。それをたらふく食わされたと言うわけですか」とわたし。「そこまでは分かりました。分からないのは、ペプシンを飲まされたことです。どうしてそれだけで、頭がおかしい泣き上戸になるのを防げたんです?」
わたしは親父をちらりと盗み見た。そして自分の目が信じられずもう一度。彼は私を愛情深い目で見つめていた。
「ざっくり説明すると」とビッグス。「プロラクチンは純粋なタンパク質であり、純粋なタンパク質はほとんどの液体に対して不溶性です。アルコールにも、水にも、皆さんが通常口に入れるいかなる液体にも。
ぼくは料理に少量のプロラクチンを振りかけました。ただし、味方に関してはホルモンの影響を受けないようにしたかった。そこでペプシンが登場するわけです。ペプシンは、純粋なタンパク質を破壊し、可溶性のペプトンに変化させます。そのためペプシンは消化薬として使われるのです」
「Drwstbynlvy……」と船長がもごもごと言った。
「え? 何とおっしゃいました?」とわたし。
ビッグスは当惑した様子で言った。「何をおっしゃっているかは聞き取れなかったけど、想像は付くよ。『わしの可愛い部下たちよ。心の底から愛しておるぞ』ということじゃないかな。えーと、スパークス。船長を介助して船長室にお連れして、しばらく寝かせてさしあげるのがいいんじゃないかな」
わたしたちはそうした。だがこれ以上語るべきではないかもしれない。船長は、彼のいわゆる“愛情薬”から覚めた後、この話題についてひどく敏感になったからだ。わたしはまだサタン号でうまくやって行くつもりなのだ。
何はともあれ、これで騒動は終わった。だがハンソン船長にこの件の話は持ち出さないで欲しい。わたしが被害を被るからだ。そうなったら、わたしは冥王星行きの特急券を手に入れて高飛びするだろう。いや、わたしだけでなく、ビッグスも。今やハンソン船長の前では“母性愛”は絶対の禁句なのである。
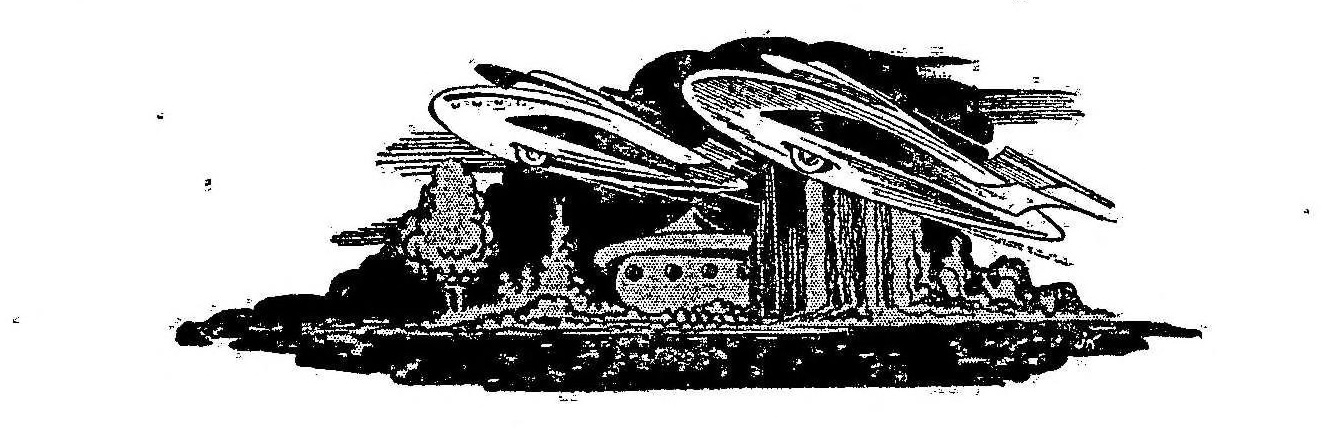
終わり